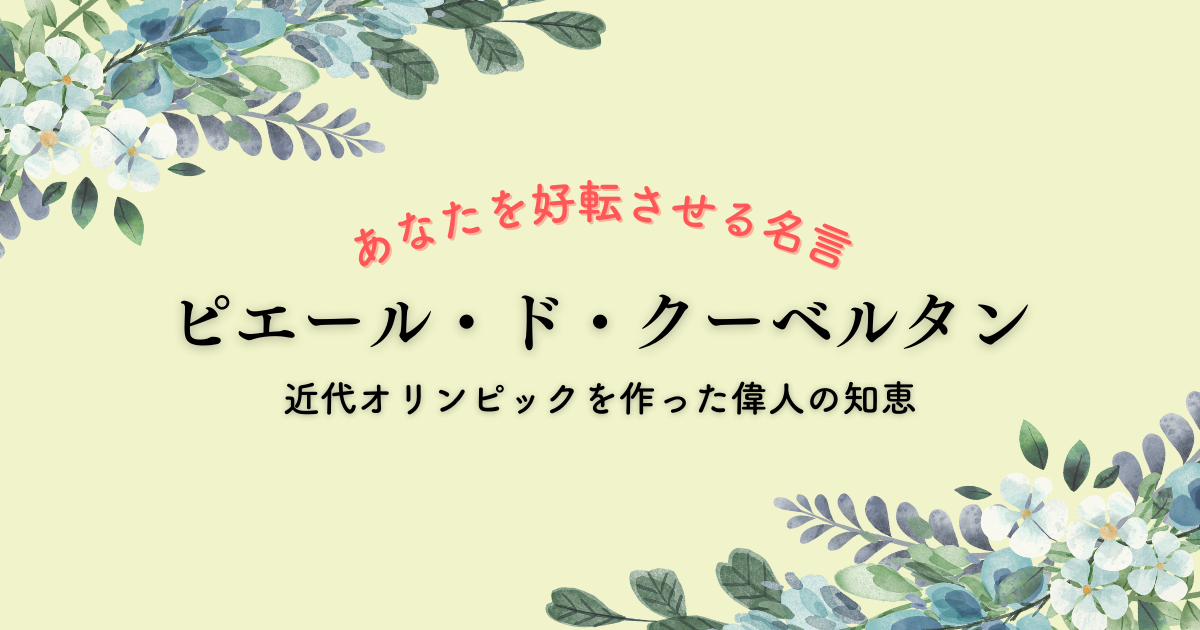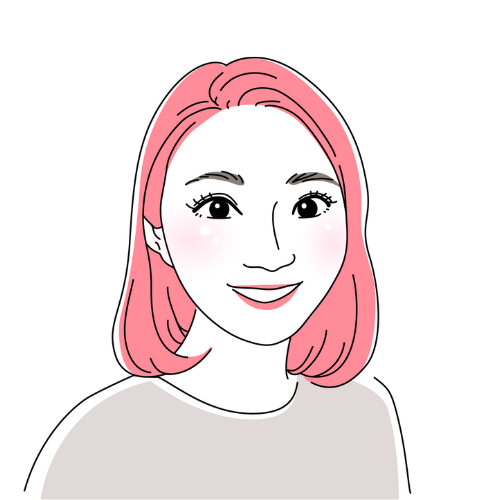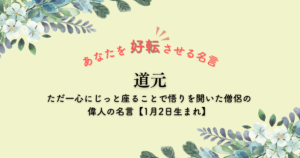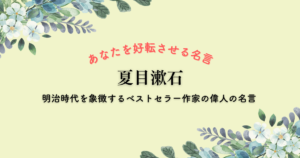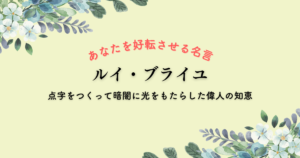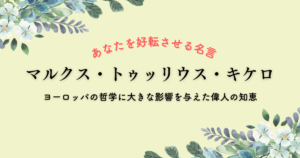【近代オリンピックを作ったスポーツの偉人の名言】
1月1日生まれ:
(1863~1937年 フランス)
大切なのは、勝つことではなく、参加すること。
ピエール・ド・クーベルタン
 友人
友人友人:ねえ、オリンピックってすごいよね!なんでオリンピックが始まったの?



ピエール:オリンピックは古代ギリシャのオリンピアっていう都市で始まったんだ。今から約52800年前に始まったんだよ。それから1000年以上続いてきたんだ。



友人:すごい歴史があるんだね!なんでオリンピックに興味を持ったの?



ピエール:子どもの頃、学校の先生から古代ギリシャの文明について教わって、とても関心を持ったんだ。12歳のときに、ドイツの考古学者がオリンピックの遺跡を本格的に発掘し始めたんだ。それまで地中に埋もれていた競技場や神殿が姿を現し始めたんだよ。すごくワクワクしたんだよ。



友人: その時期は戦争があったんだよね?それがなぜオリンピックにつながったの?



ピエール:当時、ヨーロッパでは戦争が続いていて、フランスでも人々が希望を失っていたんだ。だから私は人々を元気づけたくて、教育の道を志すようになったんだ。



友人: それでいろんな国の教育を学んだんだよね?



ピエール:そうなんだ。その中でイギリスのある学校に出会ったんだ。そこでは子どもたちがスポーツを楽しみながら体を鍛えるだけでなく、道徳や社会のルールも学んでいたんだ。すごく感動したんだよ。



友人: それでオリンピックを復活させるアイデアが生まれたんだね。



ピエール:そうなんだ。教育にスポーツを取り入れるだけでなく、戦争の代わりに世界中の若者たちがスポーツの競技会をすることがいいんじゃないかと考えるようになったんだ。そうしてオリンピックを復活させるアイデアが広がっていったんだよ。



友人: 最初はみんなあんまり真剣に考えてくれなかったんだよね?



ピエール:そうなんだ。最初は誰も私の意見を真剣に考えてくれなかったんだ。でも私はくじけるこことなく、たくさんの手紙を書いて世界中を回り、説得に努めたんだ。そしてついに1896年、ギリシャのアテネで第1回オリンピック大会が開かれたんだ。



友人: それは素晴らしい!オリンピックって勝ち負けだけじゃなくて、参加する国がスポーツを通じて競い合うこと自体がすごく意義深いんだよね。



ピエール: その通りだよ!勝ち負けだけじゃなくて、世界中の人々がスポーツを通じて交流し、互いを尊重することが大切なんだと思うんだ。オリンピックにはメダルよりも尊いものがあるんだよ。これはスポーツだけの話じゃなくて、何かに真剣に挑戦しているとき、人は輝くんだと思うんだ。



友人: 本当にそうだよね。「参加すること」自体が、すでにすごい力を持っているよね。明日からも元気が出る言葉を、ありがとう。
「大切なのは、勝つことではなく、参加すること」の名言はあなたはどんな時に使える?
この【大切なのは、勝つことではなく、参加すること】という名言を、あなたが日常のこんなシーンに使うと、こんな風に喜んでもらえるのでは?という、おすすめの例を3つ!
✅学校のスポーツ大会で、運動が苦手だな…と気が引けていた自分や友達がいたが、参加することでまず100点と勇気を持って出場し、友達の声援を受けて自信をつけることができた。
✅自分や友達が、苦手な企業のプロジェクトチームのトピックがあったが、まず参加が大事と、一人ひとりが力を合わせて取り組んだところ、持ち合いのアイデアを組み合わせて、成果を出すことができた。
✅学校の文化祭で、または、コミュニティのイベントで、イベントごとは、自分や友達が休みたくなるれほど苦手だったが、とにかく参加すると、個々の才能やアイデアを発揮し、たくさんの人と知り合うこともできて、たくさんのことを学び、一体感のある素晴らしいイベントを作り上げることができた。
もちろんこれ以外でも、ふと思いついたときが、ベストタイミングですので、
自分も周りの方も「言葉の力で」たくさん勇気付けていきましょう!
ピエール・ド・クーベルタンの知っていると自慢できる背景
クーベルタン男爵(ピエール・ド・フレディ)の家族はもともとイタリアから来た。パリ7区のフォーブル・サンジェルマンの西部、ウーディノ通り20番地で生まれ育ち、イエズス会の学校に通った。イングランドのパブリックスクール教育に関心を持ち、ワーテルローの戦いでイングランドがフランスに勝利したのは、心身ともに鍛えられたパブリックスクール教育の賜物だと記している。
ラグビースクールを訪れた際、ラグビーに惚れ込み、自らもプレーを始めた。その後、ラグビーのレフリーの資格を取り、主にパリの試合で笛を吹いた。彼は社会進化論の信奉者で、優れた人種が劣った人種に社会的利益を与えてはならないと考えていた。また、1936年のベルリン・オリンピックでナチス・ドイツが見せた熱狂を非常に喜んでいた。クベルティンは、「ベルリン大会は、アドルフ・ヒトラーの強さと規律に照らして、その後の大会の規範となるべきだ」と考えていた。クーベルタン男爵(ピエール・ド・フレディ)の後継者であるアベリー・ブランデージや、フアン・アントニオ・サマランチ(フランコのファランヘ党員)も右翼思想家であった。
近代オリンピックを作った偉人の名言の知っトク由来
クーベルタン男爵(ピエール・ド・フレディ)は、歴史教科書のオリンピック祝典の記述に触発され、「ルネッサンス・オリンピック」の演説で近代オリンピックを提唱した。彼の支持によって国際オリンピック委員会(仏:CIO、英:IOC)が設立され、1896年のアテネオリンピックにつながった。自身も1912年の第5回ストックホルム大会の芸術部門で金メダルを獲得しており、「ホロ&エッシェンバッハ」のペンネームで芸術部門の文学部門で優勝したと言われている。その時の出品作が「Ode au Sport」(日本語では「スポーツ讃歌」)だったと言われている。しかし、これが本当にクーベルタン自身の作品であるという確証はなく、実際、いまだに不明である。
また、近代五種競技を考案・提唱し、1912年のストックホルム五輪でオリンピック種目として採用された。
「オリンピックとは勝つことではなく、参加することである」という言葉は有名である。この言葉は、実は、ペンシルベニア聖公会のエセルバート・タルボット大主教が、1908年のロンドン五輪でアメリカの選手たちに語ったものである。
1908年のロンドン大会当時、米国と英国は対立関係にあり、米国選手団はロンドン到着後、さまざまな嫌がらせを受けた。落胆したアメリカ選手団は、気分転換に聖体拝領を受けにセント・ポール大聖堂に行き、そこで説教に大いに励まされた。これに感銘を受けたクーベルタン男爵が、各国のオリンピック関係者を招いた晩餐会のスピーチでこの言葉を引用したところ、たちまち「クーベルタン男爵のスピーチ」として有名になり、世界中に広まった。このセリフが「クーベルタン男爵のスピーチ」として有名になり、世界中に広まったというのが真相である。