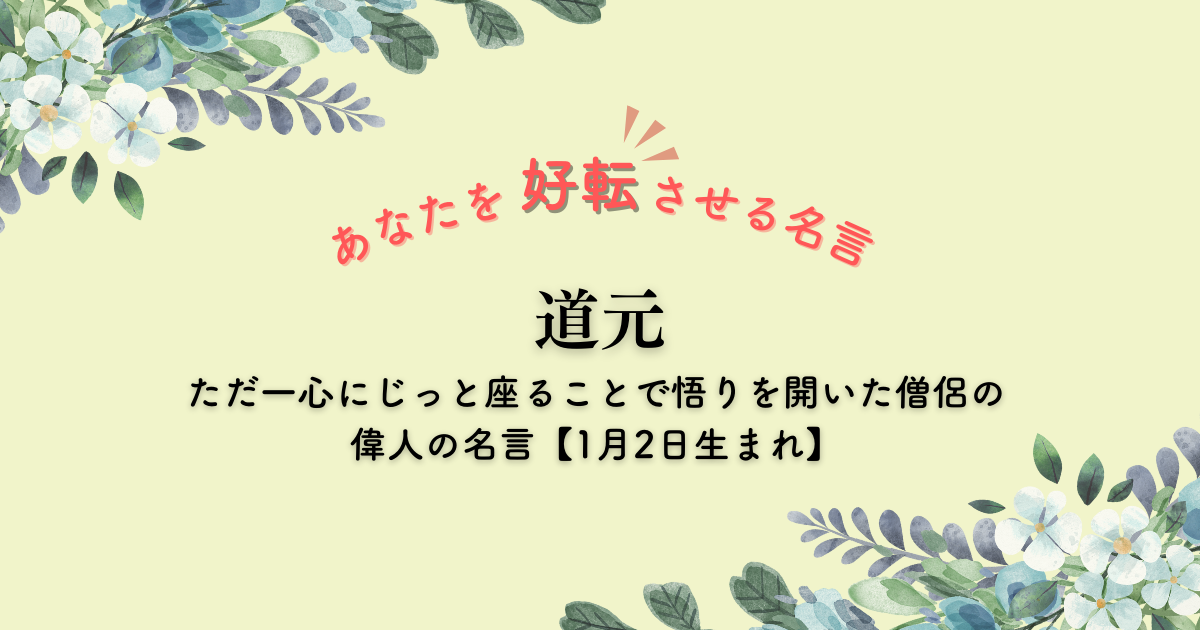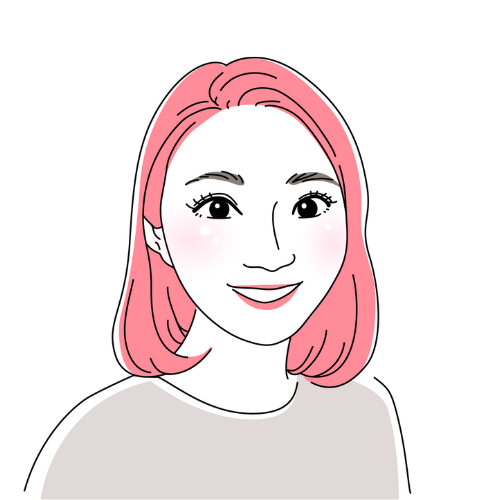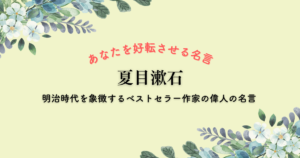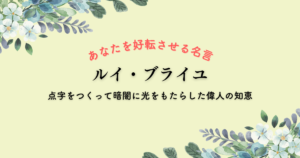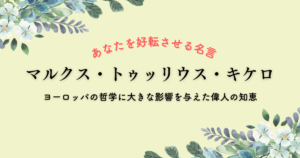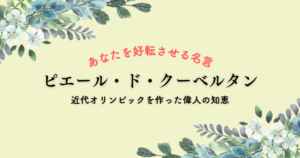【ただ一心にじっと座ることで悟りを開いた僧侶の偉人】
1月2日生まれ:
(1200~1253年 日本)
真実の自分になる。自分の真実を生かす。
道元
 友人
友人道元、あなたの人生についてダイジェストで聞かせてもらえるかしら?
うん、生まれは貴族の家だったんだ。でも、小さい頃に父と母を失ったんだ。特に母の死は辛かったな。彼女のお葬式の時に、人の命ははかなく、世の中は変わるって感じて、何もできない気持ちになったんだよ。



幼少期は辛かったね…その後どうしたの?



そこから仏の道に入ることを考え始めて、15歳でお坊さんになる決心をしたんだ。家を抜け出してお寺に入ったんだけど、そこでは権力争いが絶えず、本当の仏の教えを学ぶことができなかったんだよ。だから、日本中のお寺を旅して正しい教えを探すことにしたんだ。



すごい決断だね。それで自分の中でその教えは探せたの?



ついに中国にまで行って修行をしたんだ。中国でもいろいろなお寺を回って、ついに「只管打坐」という教えに出会ったんだ。それだけを身につけて日本に戻って、京都のお寺で教えを広めたんだけど、権力争いに巻き込まれるのが嫌で、越前(今の福井県)に大仏寺を建てて、心を込めて教えを伝えたんだ。それが曹洞宗の始まりだよ。



なるほど。大きな影響を生んだんだね。あなたの一生をかけての発見は「好きなこと、嫌いなこと、欲しいもの、これが欲しい」とか関係なく、ただひたすら座って見つめることで、本当の自分になれるってことなんだね。そこで体感した「真実の自分になる、自分の真実を生かす」ってことが大事だよって伝えてくれてるんだね。どの時代も人はそのときの周りの価値観に流されがちで一生を暮らしてしまうからなのか、時代や国を超えて悟りに近い人は同じようなことを伝えるから、真髄でありとても深いメッセージだね。
名言で勇気づけ!道元の「真実の自分になる。自分の真実を生かす。」はあなたはこんな時に使える!10選!
この【真実の自分になる。自分の真実を生かす。】という名言を、あなたが日常のこんなシーンに使うと、こんな風に喜んでもらえるのでは?という、おすすめの例を10個!
✅仕事や学業で困難な状況に直面したとき、「真実の自分になる。自分の真実を生かす。」という道元の名言が友人に勇気を与え、周りに流されずに、「自分の強みを信じて乗り越える」助けとなる。
✅自己成長を目指す際に、「好きなこと、嫌いなこと、欲しいもの、これが欲しい」とかまわず、ただひたすら自分を見つめることで、自分の本当の気持ちに気づくことができると友人に伝えることで、彼らを前向きな方向へ導くことができる。
✅恋愛や人間関係の問題に直面したとき、「真実の自分になる。自分の真実を生かす。」という名言が、友人に「自分の気持ちを素直に表現していいんだ!」という勇気を与え、余計な詮索をしないで、周りと良好なコミュニケーションを築く手助けとなる。
✅ 精神的な困難に立ち向かう際に、「自分の本当の価値を信じて」、「好きなこと、嫌いなこと」にとらわれず、自分自身を大切にする姿勢を持つように促すことができる。
✅自分の夢や目標に向かって進む際に、「真実の自分になる。自分の真実を生かす。」という道元の名言が、友人に「自分の道を信じる力」を与え、「努力を続ける意欲」を高めることができる。
✅自分の価値や能力を見極める際に、「真実の自分でいいんだ、それを生かすんだ」というメッセージが自己肯定感を高め、自分の強みを活かす自信をもたらすことができる。
✅自分の過去の失敗や挫折に対して、もう目の前にはない過去を引きずらず、その経験があったからこそ、もっと自分を見つめる機会ができ、「真実の自分になる。自分の真実を生かす。」ことができるので、この道元の名言が、友人に「過去を受け入れ、未来に向かって前進する勇気」を与えるでしょう。
✅健康や全体的に豊かになっていくことのウェルネスへの取り組みで、道元の名言が、友人に「自分の本当のニーズを見極め、バランスの取れた生活を送る」ヒントを提供する。
✅新しい挑戦や冒険に向かう際に、「真実の自分になる。自分の真実を生かす。」という名言が、友人に他の価値観に振り回されず「自分でいいんだ」という自分自身を信じる勇気を持たせ、新たな可能性に向けて踏み出す刺激となる。
✅ 周囲の期待や社会の常識にとらわれずに自分らしく生きたいとき、道元の名言は友人に、「自分の内なる声に徹底的に耳を傾ける大切さ」を伝えることができる。
もちろんこれ以外でも、ふと思いついたときが、ベストタイミングですので、
自分も周りの方も「言葉の力で」たくさん勇気付けていきましょう!
道元の知っていると自慢できる背景
【生い立ち】
道元は正治2年(1200)、京都の公家・久我家(村上源氏)に生まれた。幼名は「信貴丸」とも「文殊丸」ともいわれるが、定かではない。仏教学者の大久保道一が提唱した説によれば、父は内大臣源通親、母は太政大臣松殿基房(藤原基経)の娘藤原伊子。上記の説で養父とされる源通親の子、堀川通嗣が道元の実父であるという説もある。四国地方には、道元が藤原家の馬小屋に捨てられているところを発見され、その泣き声が読経のように聞こえたことから神童として保護されたという伝承があるが、道元の誕生がキリストや聖徳太子の誕生と混同された結果ではないかという指摘もある。伝記『顕信記』によれば、3歳で父(道親)を、8歳で母を亡くし、異母弟の堀川道智の養子となった。
4歳で漢詩「百栄」、7歳で「春秋左氏伝」、9歳で「阿毘達磨倶舎論」を読んだ神童といわれる。両親の死後、母方の叔父である松殿四家(元大臣摂政)から松殿の養子になることを勧められたが、道元は世の無常を感じ、僧侶になることを望んだため、その申し出を断ったという逸話がある。
一心に座ることで悟りを開いた偉人(道元)の名言、知っトク由来!
道元禅師の思想の核心は、ひたすら坐禅を組むことによって悟りが開けるという立場にあったと言われている。道元禅師の立場は「修証一休」「本証妙証」と呼ばれ、その思想は『正法眼蔵』全75巻に見られるが、晩年の『正法眼蔵』全12巻では因果応報や出家主義を強調するようになる。
しかし、晩年の『正法眼蔵』12巻では、因果と出家主義が強調されるようになった。仏性は一定の悟りを得て完成するものではなく、成仏した後もさらなる悟りを求めて終わりなき修行を続けること(修証一如)が悟りの本質であり、仏に従って坐禅に精進することが最良の修行であると主張した。
鎌倉仏教の大半は末法思想を肯定しているが、『正法眼蔵随聞記』には「今、吾が言ふことは、全く吾が言ふことに非ず。仏教における『正像松』の原則に固執するのは、一時的な便法に過ぎない。それ以外に真の道はない。すべてはそれに従わなければならない。この世のディヤーナが他のすべてのものよりも優れているとは限らない。不思議なことに、心が浅く、根が低い者がいる。邪悪な衆生とその低い根のために、釈尊は様々な戒律と法の教えを授けられた。すべての人は仏法の器である。しかし、仏法に従えば、必ず悟りを開くことができる、としている。
南宋で師事した天童如浄はある日、坐禅中に居眠りした僧から「坐禅はすべて身心解脱であるべきだ」と諭され、大いに悟った。身心解脱」とは、心身があらゆる束縛から解き放たれて自由になること。道元禅師が悟りを開くきっかけとなった「身心解脱」という言葉は、曹洞宗の真髄を表している。
道元禅師は、禅僧として初めて義浄土を実践した。
道元禅師の易行道(浄土教の一つ)に対する見解は否定的である。
道元は法華経を特に重視した。法華経は正法眼蔵随聞記で最も頻繁に引用される経典である。晩年、道元禅師は不治の病を患い、永平寺を離れて弟子たちと暮らし、その住まいを「妙法蓮華経庵」と名付けた。亡くなる直前、道元禅師は『法華経』のいわゆる「道場偈」(『法華経』如来神力篇第21偈の「和歌を唱えよ」から「正仏を唱えよ」まで)を低い声で唱えながら室内を歩き回り、柱に「妙法蓮華経庵」と書き添えたという。
単に視覚や聴覚を追求するのではなく、坐禅そのものが「成仏」であり、修行そのものが「悟り」であるという禅の思想を説いた。