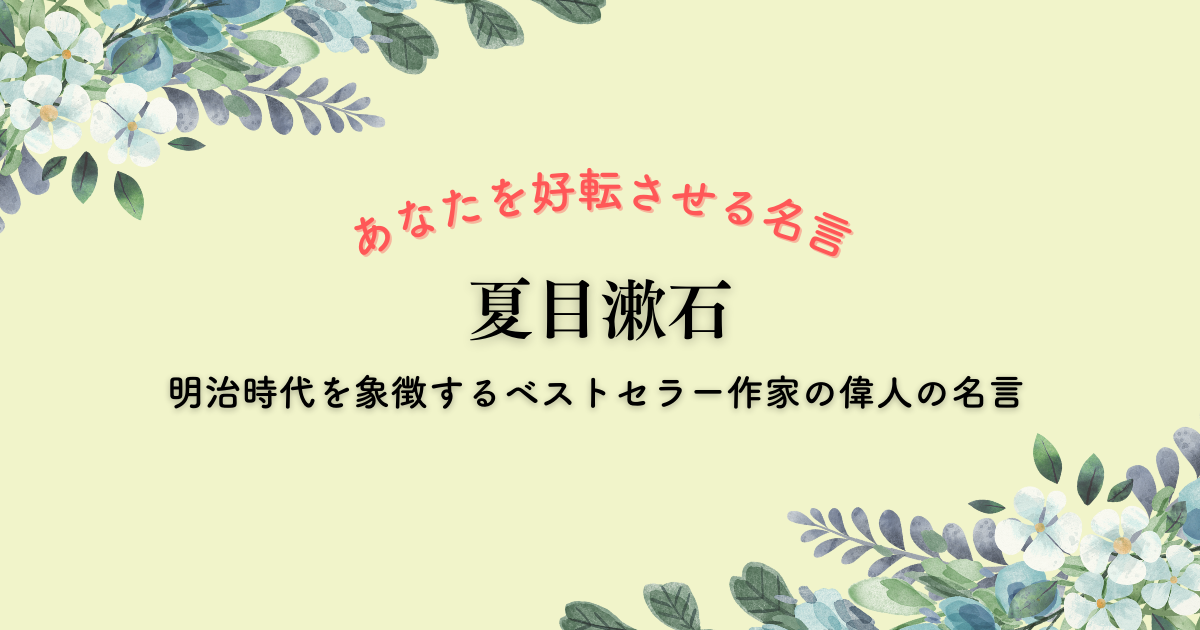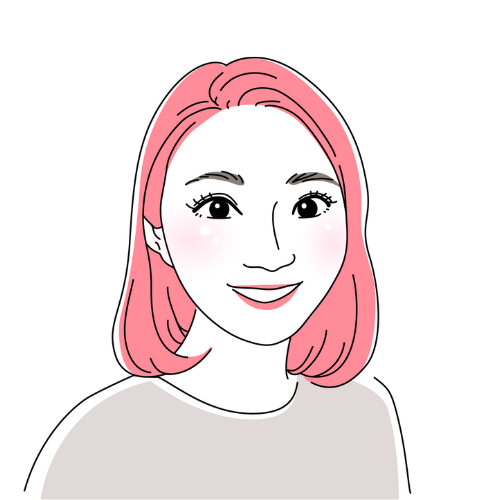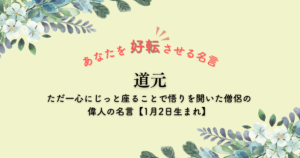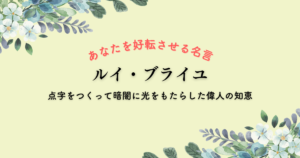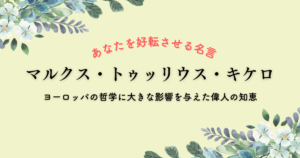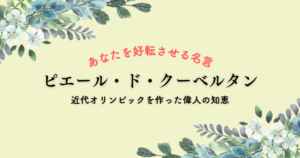【明治時代を象徴するベストセラー作家の偉人の名言】
1月5日生まれ:
(1867年〜1916 年)
あせってはいけません。
夏目漱石
ただ、牛のように、
ずうずうしく進んでいくのが大事です。
 友人
友人友人: 夏目さん、千円札に載っていたことを知ってるよ!でも、実は生まれた家庭から養子に出されたっていうのは初めて聞いたな。どうしてそうなったんだろう?



夏目漱石: 実は、私が5人目の子どもだったからだよ。家の経済的な事情もあったみたいで、生まれてすぐに養子に出されたんだ。一度は実家に戻ったんだけど、またすぐに養子に出されたから、実の両親をおじいちゃん・おばあちゃんだと思っていたんだよ。



友人: そりゃさびしい思いをしたね。でも、英語の勉強は得意だったんだね。帝国大学の英文科に進んだんだから、すごいじゃない!



夏目漱石: ありがとう。実は英語は得意だったんだ。その後、イギリスに留学して英語の教師になるつもりだったんだけど、ノイローゼという心の病気にかかり始めてしまったんだ。留学中に病気が悪化して、2年で帰国しなければならなかったんだよ。



友人: それは大変だったね。帰国後も教師を続けたの?



夏目漱石: 教師を続けたのだけど、どうも私の授業はつまらなかったみたいで、生徒からの人気もなかったんだ。そして、ある教え子が自殺してしまうという事件もあり、心の病気がますます悪化していったんだ。



友人: それは辛かったね。でも、心の病気を治すために小説を書いたってことは知ってるよ。『吾輩は猫である』でしょ?有名な小説だよ。



夏目漱石: そうそう、その小説を書いたんだ。実は気晴らしに書いたんだけど、それが評判になって、小説を書き続けることを決めたんだよ。その後は朝日新聞社に入社して、物語を書き続けたんだ。



友人: ほんとうに夏目さんの小説は興味深かったし人気だったよね。人間の心の中の悩みや苦しみを描くっていうのは、なかなか難しいことだと思うけど、どうやってそんなテーマを表現していたの?



夏目漱石: そう、人間の心の奥深さを表現するのは確かに難しい課題だよね。私は自分自身の経験や周りの人々の物語からインスピレーションを得ていたんだ。悩みや苦しみは誰にでもあるもだから、それを小説の中でリアルに描くことで、読者の共感を引き出したいと思っていたんだ。



友人: なるほど、身近な人々の物語からインスピレーションを得ていたんだね。それによって、読者が共感できる作品になったってことなんだ。夏目さんの小説はたくさんあるけれど、特におすすめの作品はどれかしら?



夏目漱石: おすすめですか…難しい質問だね。私の作品の中でも、『坊っちゃん』や『こころ』は人気があるし、自分自身も思い入れがあるんだ。ただ、それぞれの作品によってテーマやスタイルが異なるので、読みたいジャンルや興味のあるテーマに合わせて選んでもらえればと思ってういるよ。



友人: なるほど、『坊っちゃん』や『こころ』ですね。興味が湧いたので、ぜひもう一度読んでみるね!夏目さんの作品には人間の心に迫る描写があるから、きっと、その時ごとに深く考えさせられることがあると思うから、同じ小説でも全く違う感覚になりそう。ありがとうございました!
夏目漱石の知っていると自慢できる背景
【生い立ち】
夏目金之助は1867年1月5日、東京都新宿区菊井町(当時は江戸・牛込馬場下)に夏目直勝と神戸千枝の末っ子(五男)として生まれた。錦之介の父は牛込から高田馬場一帯を治める大名であった。かなりの権力と財産を持ち、公事や民事訴訟を門前で裁いていた。しかし、錦之介の母は子だくさんで高齢出産のため内気だった。
錦之介の名前「錦」は、生誕57周年につけられた。「錦」の字は、この日に生まれた子は大泥棒になるという迷信から、厄除けの縁起物としてつけられた。
錦之介の祖父・夏目直樹は浪費家で、アルコール中毒で死んだと言われている。しかし、父・直勝の努力によって、夏目家はかなりの財産を築くことができた。しかし、明治維新後、夏目家は混乱と衰退の時代を迎えたと言われている。錦之介は夜中まで荷物のそばで眠り、心配した姉に連れられて実家に帰ったという。
【子供時代】
5人兄弟の5番目として生まれた夏目金之助は裕福な家庭に育ったが、生まれてすぐに養子に出された。少年時代はとても寂しく、実の両親を祖父母のように思っていた。
勉強、特に英語が得意だった。帝国大学(現東京大学)で英文学を学び、英語教師になった。しかし、この頃から次第にノイローゼと呼ばれる心の病に悩まされるようになる。イギリス留学中に病気が悪化し、帰国後は教師として働きながら病状が悪化した。
精神的な病を治すため、彼は執筆活動に没頭し、『吾輩は猫である』という小説を書いた。この小説は非常に有名になり、後の作家への道を開いた。
【少年時代】
夏目金之助は12歳で東京府立第一中学校の普通科に入学した。しかし、この学校には英語の授業がなかったため、漢学と文学を学ぶために中退し、二松学舎(現・二松学舎大学)に入学した。
しかし、長兄が文学志向に反対し、出世を望んだため、二松学舎には長く通わず中退。その後、英学塾に入り、英語の勉強を始めた。
1884年、大学入学資格検定予備課程に入学。試験当日、友人から解答を教わったこともあり、合格することができた。英語も堪能で、学業も優秀であった。
以上が夏目金之助(漱石)の幼年期、少年期の概要である。苦難の少年時代を経て、学問の道に進み、才能を発揮した。精神を病みながらも執筆活動に打ち込んだ。
【青年期】
1886年、大学予備門が第一高等中学校と改称された頃、夏目金之助は虫垂炎にかかり、進級試験を受けることができなかった。受験には失敗したが、英語教師や塾講師として自活を続けた。
学業にも励み、多くの科目でトップクラスの成績を収めた。特に英語の才能は傑出しており、他の生徒たちと「十人の会」というグループを作り、学問の輪を広げていった。
【作家時代】
文学の道を志した夏目金之助は、1889年に夏目漱石のペンネームを使う。多くの小説を書き、作家としての地位を確立した。
彼の作品は娯楽性だけでなく、人間の心の内面的な悩みや苦しみ、正義や道徳の問題にも触れていた。彼の小説は広く読まれ、高く評価された。
夏目漱石は日本文学史上重要な人物となり、その作品は今も多くの人に愛され続けている。彼の生涯と作品は、彼自身の苦難と成長の物語でもある。
以上、夏目漱石の幼少期と作家としての歩みを概観した。幼少期の困難を乗り越え、その才能で日本文学に大きな足跡を残した。